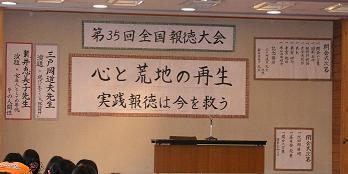 |
<会場準備> 正面に全国報徳大会の掲示 右側(上手)に開会式次第/閉会式次第
|
|
<展示> 会場入り口には小田原報徳実践会の活動内容
|
<展示> 小田原市内小学4年生の報徳学習の掲示 |
|
<報徳太鼓> 12;30 バスが到着 正面玄関では、小田原報徳太鼓の子どもたちが |
 |
| <国歌斉唱・報徳訓朗誦> 13:00開会 国歌斉唱につづき、報徳訓を朗誦しました。  |
 |
| 報 徳 訓 父母の根元は天地の令命に在り 身体の根元は父母の生育に在り 子孫の存続は夫婦の丹精に在り 父母の富貴は祖先の勤功に在り 吾身の富貴は父母の積善に在り 子孫の富貴は自己の勤労に在り 身命の長養は衣食住の三に在り 衣食住の三は田畑山林に在り 田畑山林は人民の勤耕に在り 今年の衣食は昨年の産業に在り 来年の衣食は今年の艱難に在り 年々歳々報徳を忘れるべからず |
|
|
<会長挨拶> 田嶋 享 尊徳翁生誕の地小田原で全国報徳大会が開催
|
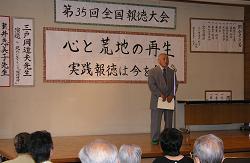 |
|
<表彰> 功績顕著者 大会出席回数表彰者 |
 |
|
<来賓挨拶>
|
<来賓挨拶> 小田原市長 加藤憲一  ここ尊徳記念館の周辺には、油菜植栽地、捨て苗 育成地など先生の40年あまりの空間が残っている。 小田原は後年先生と断絶してしまった土地でもあるが 現在、当時より深刻な荒廃が進んでおり、小田原市政 も財政難で難しいかじ取りを迫られている。 徳を活かす市政、地域のコミュニティ単位で地区を どうつくっていくかが課題となっている。 小田原市には25連合自治体があるが、どうやって いくか、先生が200年前にやっていたことを現代に やき直していくことが大事なことだと思っている。 365日一日一文でやっていく。 市民への報徳の教えの浸透は足りない。よその人に 恥ずかしくない活動をしていきたいと思っている。 各地での報徳の活動がますます発展することを祈り 挨拶とします。 |
| <来賓挨拶> 南足柄市長 沢 長生  足柄の金太郎と金次郎、似たような名前ですが。 足柄では報徳仕法を何箇所かでやっている。 『道徳無き経済は犯罪である。 経済無き道徳は寝言である。』 せめてこれからの時代、経済か人のためになり 少なくとも会社の発展と、人の幸せの両立を、 大事にしたい。 努力、勤労を軽視しているように思う。 勉強が必要、我慢が必要。 道徳を教育と置きかえると良く見えてくる。 報徳の教えを日本人にしてほしい。 皆さまの活動が国を変えていくのではないで しょうか。 |
<来賓挨拶> 神奈川県会議員 磯貝敏彦  (前略) 宝永の大噴火で荒廃した地を尊徳翁が復興。 笑顔であいさつ ありがとう お先にどうぞ もったいない 使った道具はもとに戻す 神奈川県の道徳教育に使おうと思っている。 |
| <来賓挨拶> 小田原市議会議長 志沢 清  (前略) 小田原市では、尊徳学習や、市民大学を やっている。 このような活動で民間団体と行政が 一円融合することは素晴らしいことです。 ますますのご発展をお祈りします。 |
<来賓挨拶> 鳥羽市から 元市議会議長 竹内 久 扇芳閣社長、めだかの学校校長 谷口仙二  去年、鳥羽市の偉人・世界の真珠翁御木本幸吉 の150周年祭を行った。 幸吉翁は、尊徳翁を経営の理念にしており、 今年、扇芳閣内のめだかの学校に金次郎の像を 設置した。そして生誕地小田原と交流を図りた いとご相談して今日の参加となった。 めだかの学校は、小田原が発祥の地です。 大人と子どものかかわりができ、親子の触れ 合いの場としてめだかの学校を作った。 ここは出会いをキーワードにした場です。 |
| 鳥羽市より友好の印として あこや貝の灯りをプレゼント 御木本の了解を得て、交流のシンボルとして アコヤ貝の灯りを贈ります。 これを機会に報徳団体と御木本幸吉の 鳥羽とが交流し大きなうねりとなることを 期待しています。 |
 |
| <祝電紹介> 横浜市長 中田 宏 皆さまの教えに敬意を。 |
|
| <参加団体紹介> 「添付の資料で参加団体の紹介にかえます。」 |
財団法人北海道報徳社(北海道) 2名 牛首別報徳会(北海道) 2名 茂木報徳会(栃木県) 1名 二宮報徳会(栃木県) 1名 横浜報徳さくら会(神奈川県) 2名 財団法人中央報徳会(神奈川県) 1名 学園花の村(神奈川県) 2名 株式会社光電製作所(山梨県) 2名 社団法人愛知報徳会(愛知県) 9名 社団法人大阪報徳会(大阪府) 4名 鳥羽市から 2名 二宮報徳会 2名 財団法人モラロジー研究所(千葉県) 1名 小田原報徳実践会 13名 |
| <記念講演> 『現在に生きている報徳精神』 作家・実業家 三戸岡道夫   現在の報徳精神ともいえる二人をご紹介する。 1.伊那食品工業 塚越寛さん 現代の経営に報徳をどう活かすかエッセイ集の企画があり、松下幸之助、ドラッガー、ケネディ、小泉純一郎など 10人を選んで執筆した。その原稿が上がった頃にマネジメント研究会で伊那食品の塚越氏を紹介してもらった。 塚越氏の会社の目的は、社員を幸福にすることにある。利益はその手段である。 これを聞いて非常に興味を持ち、急きょ塚越氏のことをこのエッセイに追加することにした。 塚越氏は、会社を永続きさせること、売上目標は無しの経営を目指しているが、社員からの要望でさすがに売り上げ 目標無しにはできないので、『前年を下回らない』ことを経営目標としている。 20年前にカンテンパパが大ヒットし、あるスーパーから業務提携の話があったがキャンセルした。 提携すれば一時は売り上げは伸びるが永続きしない。機械を増設したり、人を採用したりしたあと、5,10年経ち ブームも去ると、機械は廃棄すればいいが、人はクビを切らなければならなくなる。そういうことはできない。 売上を伸ばすためにどうしているか? 全社員の1割の人員を研究にあて研究室を充実している。いろいろな寒天を商品化し売れる商品で売上を伸ばして いる。寒天で落ちない口紅もつくったりしている。 株式市場への上場圧力のあったが、塚越氏は50〜100億もいらないし、上場すると株主圧力もあり100%経営に 注力できなくなるとして、上場をしていない。 塚越氏の経営は、現代をリードする報徳精神といえる。 2.海外の二宮金次郎といえる モハメド・ユンス氏(バングラディッシュ) ユンス氏は、バングラディッシュでグラミン銀行をつくりソーシャルビジネスを実践している。 *経済学者、2006年ノーベル平和賞 故郷バングラディシュで大飢饉が起こったとき、国の為にできることないかと帰国した。 この時の状況は、金次郎が桜町へ行った時の状況と良く似ている。 当時バングラでは、1ドルで竹かごを編んで生計を立てている人々が、資金を借りるときに2ドルで売るという条件で 貸し付けを受けてていた。銀行家はこれを4ドルで売って儲けていた。 42人が27ドルを借りて、借金を返せない状況となっていた。 ユンスは、27ドル貸して高利貸しに返し清算させて借金から解放した。 このときに担保なしで、五条講を作った。現在、200万人の人たちが借りている。 *五条講:講とは、江戸時代一般の人たちが零細な資金を持ち寄り一人に貸し与え事業資金にするものだった。 尊徳が示した五条は、金の貸し借りに対し人間が守るべき五カ条を示した。 もので、信・仁・義・礼・智からなる。 信ー金銭の積み立てと賃借の約束を守ること。 仁ー資金の余裕ある人が囚窮者の為に出資すること。 義ー借りた人は確実に返済すること。 礼ー仁をなす人は奢り昂ぶらないこと。 智ー借りた人は返済を工夫して、講仲間の便利をはかること。 また、ヨーグルトを子どもに食べさせたいと、安く作ることを考え会社をつくった。 これは慈善事業ではないので、単に与えるだけでは自尊心の満足になり、かつ自立心も無くなってしまう。 どんな人も10〜20%は人を助けたい心があるはず。その部分をソーシャルビジネスにあてるべきである。 配当の無い会社も立派な会社である。たとえば、きれいな水を作る会社、靴を作り会社などなど。 日本は全体に豊か過ぎるからこんな考えの入る余地がない。 金次郎の教えは、農民に蓄積され、自分には残らなかった。 これは、21世紀の世界経済の思想といえるのではないか。未来の地球を救う思想です。 |
|
| <記念講演> 『家庭人としての尊徳・その人間性』 ノンフィクション作家 新井恵美子  私の作家になるきっかけを作ったのはに二宮尊徳。22年前に尊徳のことを知りたい、作家になるために尊徳のことを 知りたいと小田原に来た。 尊徳は222年前にここで生まれた。女性から見た尊徳のことを知りたいと思った。 江戸時代の女性について、調べようと思っても資料は全くない。ところが尊徳全集の34巻に、生活にかかわることを 発見した。ここに二宮さんちの家計簿があった。 この家計簿からわかったことは、600もの仕法を成し遂げた基本は、家計にあったということ。 それは、皆がよくやっているあたりまえのことだった。 *尊徳全集は、大正時代、佐々井典比古氏のお父上が、尊徳の書き残した小さな切れ端まで全部本にしたもので、 「報徳博物館」インターネットで一部を見られるようになっている。 報徳博物館のHPは、http://www.hotoku.or.jp/index.php 日記と家計簿から一人の男が浮かんできた。尊徳は記録魔で、よその家を訪問したら何で出たかを詳しく記録している。 たとえば栢山の祝い事では、「アジが300匹出た」浜から持ってくる魚は貴重で、これは小田原の漁業史だともいえる。 金次郎の父はダメおやじだった。 ダメおやじの当時の定義?は酒が好き/病気がち/学問が好き(農民なのに) →子どもを不幸にしたオヤジはダメ。 でも、金次郎の父は、ちょっといいことをした。金次郎にいつも言っていたことは、 『並みの百姓で終わるな。理想を持って生きなさい。』 金次郎は、14才で父を亡くし、16才で母を亡くし、20才で家にようやく自分の家に帰って来た。 何で貧乏になったか? ー父がやる気をなくしていた。酒匂川氾濫が原因?−自分の家だけだから原因ではない。 −当時は病気で長患いすると死んだときに医療費が発生する。 →土地を村田先生のところに持って行きそれで支払いをしようとした。 →村田先生は、生活ができないだろうと半分返してくれた。 *この土地のことから、冠婚葬祭はくだらないと江戸時代に気がついた。人に会って学ぶ、いやなことからも学ぶ →金次郎は文化三年に借金をして家を建て直してゆく。これが私の家計簿のはじまり。 半紙を二つ折りにして控帳をつくった。(原本は国会図書館にある) 金次郎は、やるぞ〜と思い、自分は幸せだと思った。自分には「親が失ったものを取り返す」という目標があるから。 4年で家を新築し、土地を取り戻し、お伊勢参りまでやってしまった。 *お伊勢参りは当時はステータスだった。人生の目標としてお伊勢参りがあった。 善種(いまでいうFund):栢山ではタダの焚き木を持って10km歩いて小田原で売ると高く売れた。 金次郎の妻 波子さん(飯泉)とは夫婦の価値観が一致していた。 夫婦は「船」 世間は冷たいけど船の中はあたたかい、そんな家庭を求めていた。 分度・推譲について、 私ははじめはイヤな言葉だと思っていた。人は分に応じて生きればいい?と思っていたが、分に応じた生活を! 10稼いだら8で生活し2は人に与える。 金次郎は奥さんに2両の帯(1両5万円で計算すると10万円の帯)を買っている。 実はこの頃の金次郎さんは分度が大きくなっていた。サブプライムローンは、10に12貸し付けている米国の実態。 積小為大 当たり前のことだが小さなことが大事。 たとえば1回遅れてくると許してくれるが2回3回となるとあの人はダメだということになる。 一日一個覚える。それが積もり積もって大きなことになる。 金次郎の最初の仕法は、家を建て直したことと思う。 四年で立て直したあと、家計簿に「ゆ」という言葉がよく出てくる。金次郎はお風呂が好きで小田原の町に出来た風呂 に43回行っている。750円/回だった。 実は、風呂は男のたまり場で情報が集まっていた。 文化文政の時代、小田原が繁栄していた。風呂の情報で大久保忠真が名君で民のことを思ってくれる人と聞きこんだ。 金次郎は、この人に会いたいと思った。それを実現している。 そして、桜町へ。すべてを売りに出して桜町へ行った。そんな必要はなかったが自分の後を切って行った。 桜町へ行く時、金次郎は波子さんに「私は行きたいがどうするか」と聞いた。 波子さんは、「私はあなたの行くところはどこでも行く」と言った。金次郎はご褒美に、桜町へ赴任する途中、江の島、 鎌倉などの観光地を見せて高いお弁当を食べた。 桜町へ入るとき、結城村のあぜ道で殿様が迎えてくれた。 為徳報徳 「徳」とはそのものが持っているもの=可能性 荒地の中に徳がある 「夢」を持って荒地を耕そう。自分のやり方を殿様が理解してくれた。→ 尊徳 と 桜町での生活は、姑がいない、今でいう核家族だった。 日記に、「ふみちゃん(娘)がおもらしした。医者に行くとそういうこともあったでしょうと言われた。だから大丈夫だ。」 「ふみがはしかやった。」「やたろうがはしかやった」 当時、男は公が大事だったが、金次郎は公私混同だったかも しれない。 金次郎は、『私の家庭が、まず幸せでなくてどうして世界が幸せになる』 → 「村が」、「国が」に通じる。 金次郎は子どもに自分の職場を見せている。 リサーチするときに子どもを連れている。その帰りには戦利品にシジミを持って帰ってくる。そうすると子どもが父の 価値観を持ってくる。 子どもにひな形、設計図を残せる。 現代は100年に一度の不景気と良く人は言う。人々が閉塞感に満ちている。 金次郎の言葉に、 『入りは出たものの帰り』 がある。 親切にしてもらいたいと思ったら、まずその人に親切にする。(まず推譲する)そうすると戻ってくる。 『来るは、譲りたるものの代償』 『たらいの水は、欲しいと思うと逃げる。いらないというとぐるりと回って戻ってくる。』 金次郎は、あらゆるものから学んだ。 小田原市民は、金次郎に背を向けて生きてきたことあったが、私たちは誇りとしたい。 『明日を見ることは富む』 『先を見なさい』 → まず第一歩を踏み出す。今立っている所からスタートする。 |
|
<懇親会> 箱根湯本ホテル  歌手も登場して懇親を深めました。 懇親会での田嶋会長挨拶  参加者全員で記念写真 この後会場を移し、「芋こじ」芋をこじるように互いの意見を交換して自分を磨く会。 ざっくばらんに親しくお話をしました。 |
|
二日目史跡見学会 |
|
 |
尊徳記念館にて 展示をもとに尊徳に歴史を解説員に説明して もらいました。 |
 |
生家前広場にて 生家まえの広場で、尊徳翁の回村の像、生家 の説明をしてもらいました。 |
 |
善栄寺にて 尊徳翁の墓所がある善栄寺 |
| 二宮金次郎「少年勉学の像」 金次郎が享和三年(1803)十六歳の頃、伯父万兵衛 宅に寄宿中、一日の仕事を済ましてから、夜遅くまで書物 を読んでいるのを見て、万兵衛は、「百姓に学問は無用 じゃ」と行燈の油を無駄に使うなと厳しく叱った。 そこで、友人から菜種五勺(一握り)を借りて、仙了川の 土手に蒔き、それが翌年の春になって七升以上の収穫と なり、使いきれない程の油ができた。このことが「積小為大」 の貴重な体験になったといわれる。 この銅像はその十六歳の頃で、刻苦勉励して「小を積ん で大を為す」の自然界の心理を深く学んだ姿である。 |
 |
| 二宮尊徳先生の墓 二宮尊徳先生は、天明七年(1787)7月23日栢山の 中流農家に生まれたが、幼少の頃、酒匂川の洪水で家は 貧困に陥り、十四歳で父を、十六才で母を失った。 以後、彫苦勉励して家を再興、また抜群の才幹と卓越した 人格によって、各地方の財政復興と社会救済に偉大な業 績を遺し、すぐれた報徳の教えをたてて後世に伝えたので ある。そして、安政三年(1856)10月20日、日光神領 復興仕法中に栃木県今市の報徳役所で、その偉大な70 年の生涯を閉じ、同地の星頭山如来寺に葬られた。 この時、先生最後の病床に侍していた実弟三郎左衛門 (幼名友吉)が、遺髪と遺歯を抱いて10月26日故郷に 帰り、当時の二宮総本家の墓地の中に埋葬したのがこの 墓である。「葬るに分を越ゆるなかれ」とは。、門下に残し た遺言である。 「誠明院功誉報徳中正居士」とあるのが、先生の戒名で ある。 如意山善栄寺 |
 |
| 捨て苗栽培地 この捨苗栽培地跡は、享和三年(1803年)6月の酒匂川 大洪水によって使えなくなった用水掘に、洪水の翌年、 捨てられている植え残りの苗(捨苗)を植えつけるため、 金次郎が耕したもので、秋にはここから籾(もみ)一俵余り の収穫を得ることができたという。 金次郎はこの経験から、小さな事でも精を出して勤めて いけば、どんな大きな事でも必ず成しとげることができると いう「積小為大(小を積んで大を為す)」の法則を見い出した。 小田原市教育委員会 |
 |
| ページトップへ | |


